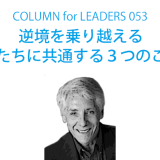「レジリエンス」(resilience)とは、人生に発生する困難な状況から回復する「心の力」のことです。「精神的回復力」「打たれ強さ」「はね返す力」「しなやかな心」「逆境を乗り越える力」など、多様な訳があてられています。
かつて「レジリエンス」は心理学の専門用語であり、限られた人だけが知るマニアックな言葉でした。それが日本で広く知られるようになったのは、2011年に発生した東日本大震災がきっかけです。2013年には、安部内閣が災害に負けない国づくり「ナショナル・レジリエンス」(国家強靭化政策大綱)を発表し、さらに広まりました。
「レジリエンス」は、心理学の世界を飛び出し、組織づくり、都市づくり、国づくりのキーワードになっています。「心の力」を意味していた言葉は、今や「場の力」をも意味します。
このコラムでは。代表的な初期の研究事例を概観し「レジリエンス」研究の「はじまり」にどんなことが考えられていたのかを把握することで、現代人に求められる「レジリエンス」をより深く理解していきます。
目次

(セルジュ・ティスロン 白水社)
「レジリエンスの父」と呼ばれる学者がいます。その学者は二人いて、マイケル・ラター(Michael Rutter)とノーマン・ガルムジー(Norman Garmezy)です。
マイケル・ラターはイギリスの心理学者です。1970年代、英国「ワイト島」に住む10歳の子どもを対象に「精神障害」の出現率に関する調査を行った人物です。数年にわたる追跡調査の結果、子どもの「精神障害」に関する「リスク因子」と「防御因子」を明らかにしました。
「リスク因子」とは、病気になる「要因」のことです。「防御因子」とは、病気になる原因から人を守る要素のことです。
「リスク因子」が増えれば病気になる確率は高まりますが、「防御因子」が増えれば、その確率を下げることができます。例えば、肺がんの「リスク因子」は「喫煙」で、「防御因子」は「運動」です。肝臓病の「リスク因子」は「アルコール飲酒」で、「防御因子」は「バランスのとれた食事」といえます。
ラターは6つの「リスク因子」を明らかにしています。
❷「低い社会階級」
❸「大家族」
❹「父親の犯罪歴」
❺「母親の精神障害の既往」
❻「子どもの施設預け入れ(里親)」
フランスの精神科医セルジュ・ティスロンは、『レジリエンス:こころの回復とはなにか』(白水社)のなかで、この研究にふれ「二つのリスク因子が併存すると発症確率は四倍に増えることを示した」(p29)と書いています。4つ重なると確率は10倍だそうです。
そしてラターは、この「リスク因子」から守る「防御因子」が効果的に働く4つの特徴を提示しました。それが、次のものです。
❷ネガティブな連鎖反応の確率を減じる
❸自尊心および固有の能力の感覚の強化
❹ポジティブな機会をもたらす
「父親の犯罪」「母親の精神障害」などがある場合、その環境は子どもにとって「困難な状況」といえます。そうした「リスク因子」がありながら「防御因子」が働くことで「精神障害」にならなかったのであれば、その子どもたちに「レジリエンス」(精神的回復力)が備わっているといえるのです。
ノーマン・ガルムジー(Norman Garmezy)は、アメリカの心理学者です。ガルムジーは「心の病」である統合失調症の研究をしていた人物で、1960年代に、統合失調症を親に持つ子どもについて調査をしています。
統合失調症になると日常的に支離滅裂な言動となります。そうした親がいる環境で子どもはどうなるのでしょうか。ガルムジーは、子どもが「心の病」になるリスクが高くなるとしつつも、9割の子どもは健全に成長していることを発見しました。
これもラターの研究と同じく、過酷な環境に負けない「心の力」を明らかにする試みであり、「レジリエンス」の研究といえます。
さて、「レジリエンスの父」がいれば「レジリエンスの母」がいます。「母」はアメリカの心理学者エミー・ワーナー(Emmy Werner)です。
彼女が行った調査についての解説が『レジリエンスの教科書』(草思社)にもありますので、『レジリエンス:こころの回復とはなにか』(白水社)にある記述も参考しつつご紹介します。
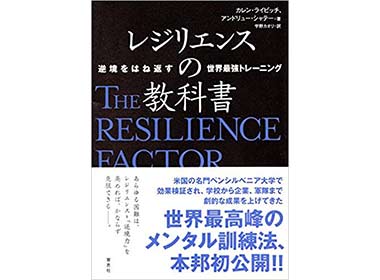
(カレン・ライピッチ、アンドリュー・シャテー 草思社)
クリックするとAmazonへ!
エミー・ワーナーの研究
1955年、ハワイのカウアイで833人の子どもが生まれました。ワーナーの研究チームは、その中の698人が30歳になるまでを追跡調査しました。698人の内、三分の一が「不利な環境」に生まれていました。
「不利な環境」とは、子どもたちが「リスク因子」を持っていることを意味します。「貧困」「親のケンカが絶えない」「親がアルコール依存症」「親の離婚」など、ラターが指摘したような「リスク因子」抱えていることです。
「不利な環境」に育った子どもたちの3人に2人に、「学習障害」「多動性障害」「非行」といった何らかのネガティブな要素が見られました。
しかし、3人に1人の子どもは、「自身に満ち、多くのことを達成し、人とつながることのできる大人へと成長」(『レジリエンスの教科書』p34)していったのです。
「不利な環境」にあっても全ての子どもが「リスク因子」に犯されて問題を抱えるわけではなく、健全さを維持する子どもの存在を証明しました。
エミー・ワーナー博士は、「不利な環境」にさらされながら健全に成長していった子どもたちの特徴を「レジリエンス」(resilience)という言葉で表現したのです。
それでは、次のページから「ホロコーストの研究」についてお話ししていきます。
「レジリエンスの父と母」がレジリエンス研究の道を開き、ホロコースト(ナチスの大量虐殺)からの生還者たちを追跡調査した研究成果が、「レジリエンス」の概念を、さらに世界に広めました。その研究を行ったのはアメリカの心理学者サラ・モスコビッツ(sarah moskovitz)です。
さて、モスコビッツの研究にふれる前に、ホロコースト研究で、より有名な考え方「SOC」がありますので、まず、それについて簡単にふれ、その後に、モスコビッツの研究についてお話しします。なぜなら、「SOC」は「レジリエンス」と深い関係があり、「レジリエンス」(精神的回復力)を高めようとする時に、とても参考になる概念だからです。
「センス・オブ・コーヒレンス」(Sense of Coherence:略してSOC)とは、「ストレス対処能力」「健康保持能力」のことです。過酷な環境を生き延びた人たちが共通してもっている特性を研究した結果、明らかにされました。
「センス」(Sense)は「感覚」で、「コーヒレンス」(Coherence)は「一貫性」です。ですので、「センス・オブ・コーヒレンス」とは、ストレスに対処し健康でいる人たちに共通する「一貫した感覚」のことです。
提唱者は医療社会学者・健康社会学者のアーロン・アントノフスキー(Aaron Antonovsky)です。
アントノフスキーは、1923年米国ブルックリンに生まれたユダヤ人で、1960年にイスラエルに移住しています。イスラエルで、ナチスの強制収容所からの生還者(女性)を対象に調査を行いました。
彼女らの約70%は、PTSD(心的外傷後ストレス)やうつ病など「心の病」で苦しんでいました。しかし29%の人たちは、健康な生活を送っていたのです。アントノフスキー博士は、この29%の人たちに着目しました。
博士は自著『健康の謎を解く―ストレス対処と健康保持のメカニズム』(有信堂高文社)のなかで、彼女たちの境遇をこう表現しています。

(アーロン・アントノフスキー 有信堂高文社)
クリックするとAmazonへ!
収容所での想像を絶するような恐怖を経験し、その後何年も難民でありつづけ、3つの〔中東〕戦争を目のあたりにした国、つまりイスラエルで人生を立て直し……それでいてなお良好な健康状態を保っているのである。
『健康の謎を解く―ストレス対処と健康保持のメカニズム』(有信堂高文社)xvii
調査対象となった彼女たちの人生は、日本で暮らす私たちでは、想像しようとしても想像しきれない過酷なものだったといえます。
では、そんな過酷な環境を生き抜いていきた彼女たちは、どんな「センス・オブ・コーヒレンス」(一貫した感覚)をもっていたのでしょうか。それが次の3つであり、「ストレス対処能力」「健康保持能力」にとって大事になるものです。
『健康の謎を解く』(有信堂高文社)では、定義がとても難解なので、精神科医斎藤環氏が「SOC」についてわかりやすく解説している著『人間にとって健康とは何か』(PHP研究所)から引用いたします。

クリックするとAmazonへ!
- 把握可能感
「自分の置かれている状況を一貫性のあるものとして理解し、説明や予測が可能であると見なす感覚のこと。 - 処理可能感
困難な状況に陥っても、それを解決し、先に進める能力が自分には備わっている、という感覚のこと - 有意味感
いま行っていることが、自分の人生にとって意味のあることであり、時間や労力など、一定の犠牲を払うに値するという感覚
『人間にとって健康とは何か』(PHP研究所)p33
いかがでしょうか。コラム「逆境を乗り越える人たちに共通する3つのこと」で解説した、「自己コントロール感」は「処理可能感」のことであり、「全てが学びと考える」は「有意味感」に通じています。
アントノフスキー博士は、人が健康になる要因・要素を考える「健康生成論」の社会学者として世に名を馳せた人だからか「レジリエンス」という文脈には登場してきません。ストレス対処に関する論では、名前が登場します。

ただ、「センス・オブ・コーヒレンス」の「3つの感覚」は「レジリエンス」(精神的回復力・逆境を乗り越える力)に通じるものですし、過酷な環境に負けない人の特性ですから、それは「レジリエンス」をも意味しているといえます。
ですので、アカデミックな分類にこだわらず、ひとりの人間としてメンタル的にタフになろうとする時、レジリエンスを高めようとする時、「センス・オブ・コーヒレンス」の「3つの感覚」は大いに参考にしてよいでしょう。
「センス・オブ・コーヒレンス」について、少々、話しが長くなりましたが、それでは、アメリカの心理学者サラ・モスコビッツ博士の研究について、お話ししていきます。
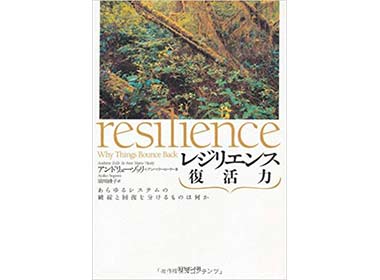
(アンドリュー・ゾッリ ほか ダイヤモンド社)
クリックするとAmazonへ!
モスコビッツの研究については、『レジリエンス 復活力』(ダイヤモンド社)で、わかりやすく説明されていますので、そちらを参考します。
サラ・モスコビッツ博士のホロコースト研究も、強制収容所を生き延びた人たちに関するものです。
1945年、英国のリングフィールド村にある孤児院に、ナチスの強制収容所を生き抜いた24人の孤児がやってきました。子どもたちは強制収容所で大量の絞首刑を目にし、人を焼いた「人灰」の容器を運ぶ手伝いをさせられていました。死体に囲まれ、むごい死臭の中で育ったのです。
博士はこの24人の子どもたちを追いかけ、その中の4人(リア、バール、ジャック、ベラ)に、1979年と1984年にインタビューを行いました。1979年時点で4人は37歳でした。
不幸な「リア」と「バール」
4人のうち2人、リアとバールは人生に多くの問題を抱えていました。リアは博士に対して、孤児院で「ぐずりや」と呼ばれて育ち、大人になってからの屈辱感、精神不安の悩みを打ち明け、不眠症であることを告げました。
バールは養子縁組が決まるものの、家庭になじめず孤児院に2度も舞い戻り、その後、アメリカに渡りました。博士が目にしたバールの姿は、重い病をいくつも抱え衰弱した無気力な中年男性でした。
2人とも、過去の出来事に苦しめられ、健康的で幸せな人生とはいえない暮らしぶりでした。
幸福な「ジャック」と「ベラ」
残りの2人、ジャックとベラは違いました。ジャックは妻と二人の子どもをもち、ロンドンでタクシー運転手の仕事をしていました。「さまざまな人と出会う毎日が冒険のようで楽しくて仕方がない」(p158)といい、幸せに暮らしていました。
ベラは結婚し、美術商のビジネスを軌道に乗せ社会的に成功していました。ベラは孤児院では、行動的な子どもで「片づけてちょうだいのベラ」と呼ばれていました。なぜなら、年上の子どもに対しても、自分がすべき片づけを上手に押しつけてしまうからです。
大人になったベラに対面した博士は、彼女をこう描写しています。
彼女は夫が心臓の手術をしたばかりだというのに、夫婦で力を合わせればどんなことも乗り越えられると信じていました。美術商のビジネスを軌道に載せ、仕事を楽しんでいました。さらには治安刑事のボランティアにも励み、子どもが関わる裁判を担当していたのです。
『レジリエンス 復活力』(アンドリュー・ゾッリ ほか ダイヤモンド社)p158-159
決して幸せとはいえない「リアとバール」に対して「ジャックとベラ」は、人生を自分の力で創り上げ、幸せをつかんでいました。その明暗を分けた特性を博士は3つあげています。
『レジリエンス 復活力』には、3つの特性に関する記述がなく、『人間にとって健康とは何か』(PHP研究所)にありましたので、ご紹介します。
- 適応力
- 大人へのアピール
- アサーティブネス(自己主張すること)
『人間にとって健康とは何か』(PHP研究所)p33
この特性は子ども時代を視野に入れている点が大きな特徴になっているのでしょう。「大人へのアピール」と「アサーティブネス(自己主張すること)」は、意味が重なっていて、結論としてのインパクトは、弱いものになっています。
ですが、過酷な環境をじっと黙って耐えるのではなく、不幸な状況を打開しようとする時に、自分を「アピール」し、「自己主張」することは、現実的で有効なスキルのひとつです。ベラは、その資質を持っていたひとりであり、博士は現実的なレジリエンス特性を提示したといえます。
レジリエンス研究の「はじまり」にある代表的な研究についてお話ししてきました。「レジリエンスの父」は2人いました。マイケル・ラター博士はイギリス「ワイト島」に住む「子ども」を研究しました。ノーマン・ガルムジー博士は、統合失調症の親を持つ「子ども」に焦点をあてました。
「レジリエンスの母」エミー・ワイナー博士は、ハワイのカウアイ島の「子ども」たちを30歳まで追いかけました。
ホロコースト研究でのサラ・モスコビッツ博士も、強制収容所を生き延びた「子ども」の存在を知り、そこから研究がスタートし、4人の「生存者」を探しだしインタビューを行いました。
どんな人であれば過酷の環境をタフに生き抜けるのか。初期の研究でも統一した見解はなく、レジリエンスの研究が進めば進むほど、多様な特性が見出されてきています。
「レジリエンスを高めよう」とする時、その特性が多くなり「あれもこれも」になると、結局、現実的に役に立たない概念になります。
お気づきのように初期の研究は「子ども」に焦点があたっています。それは、困難な状況を切り抜けるのは、「大人」より「子ども」のほうがより難しいことは明らかであり、長期の追跡調査もできますし、それ故に、レジリエンスの特性として、よりインパクトのある特性が発見できるという前提があったでのしょう。
「大人でもできなかったことを、子どもができたのは、なぜ?」
心理学者として、興味をそそられる問いです。
初期の研究が「子どもの時代の特性」に焦点をあてている事実は、私たちに「レジリエンスを高める」ヒントを届けてくれています。ヒントとは、こんな問いかけです。
人間は成長していくにつれて、多様な知識を習得し社会に適応するように価値観を形成していきます。そして「自分はこんな人間である」という「セルフ・イメージ」をつくり上げていきます。
そのセルフ・イメージは、失敗や挫折経験が多いと、とても「低い」ものになる傾向があります。「セルフ・イメージ」が低いと、メンタル的なタフさを失ってしまいます。それは「レジリエンスの低い」状態です。
そんな嘆きは大人であれば、よくあるものです。ここで、過酷な環境をたくましく生き抜いた子どもたちを見習って、考え方を変えましょう。
「子ども時代にそうであったなら、その資質は今も持っている」と認識するのです。
「トラウマ理論」は、とかくネガティブな印象がありますが、幼少期の「暗い経験」が大人になって影響を与え続けるなら、「明るい経験」もまた影響を与え続けているはずです。
また、性格論の観点から、幼少期の性格は大人になっても変わらないことを指摘することができます。

世界の三大心理学者ユングの性格論では、人の「生まれ持った性格」(キャラクター)があることが想定されていて、「後天的に身につけた性格」(パーソナリティ)と分けて考えます。
「生まれ持った性格」(キャラクター)は、生涯変わりません。そして、どんな人の「生まれ持った性格」(キャラクター)にも「強み」「長所」があると考えます。つまり、子どもの頃の「よさ」は、生涯、決して消えることはないのです。
ですから、子ども時代の「ポジティブな自分」にフォーカスしていくことは、レジリエンスを高めるヒントを与えてくれるのです。
「レジリエンス」に関して膨大な資料を読み込んだ『レジリエンス 復活力』(ダイヤモンド社)の著者アンドリュー・ゾッリは、こう書いています。
ひとりひとりのレジリエンスは、その人の信念や経験によって決定づけられているということだ。人生経験の豊かな賢者の導きによるか、身体的な鍛錬や自然とのふれあい、あるいは信仰を通した満ち足りた心理状態によるかにかかわらず、個人のレジリエンスとは、精神的な習慣である。つまり、適切な方法によれば、変化させることも、高めることもできるのである。
『レジリエンス 復活力』
(アンドリュー・ゾッリ 、アン・マリー・ヒーリー ダイヤモンド社)p171
レジリエンスとは、適切な方法によって変化させ高めることのできる「心の力」です。
ゾッリは『レジリエンス 復活力』(ダイヤモンド社)の中で、「マインドフルネス瞑想」が、レジリエンスを高めるのに有効であると、詳しく説明しています。
「マインドフルネス瞑想」については、本もたくさん出ていますし、ネットで検索すれば、「やり方」が詳しく解説されてるサイトを見つけることができます。私もコラム19「スターウォーズ」に学ぶマインドフルネス」で説明していますので、参考になさってください。
何千年も昔からある「瞑想」というシンプルな手法で「レジリエンス」を高めるられるということは、どんな人にも「レジリエンスはある」ということの証といえます。その「高い」「低い」はあっても、「高められない」「身につけられらない」ということないのです。
「Volatility(激動)」「Uncertainty(不確実性)」「Complexity(複雑性)」「Ambiguity(不透明性)」の頭文字をとって「VUCAの時代」といわれる昨今です。そんな時代だからか、「レジリエンス」が求める声は大きくなっています。
難しく考えず、シンプルに…「レジリエンス」を身につけて「VUCAの時代」をたくましく乗り越えていきましょう。
(文:松山 淳)