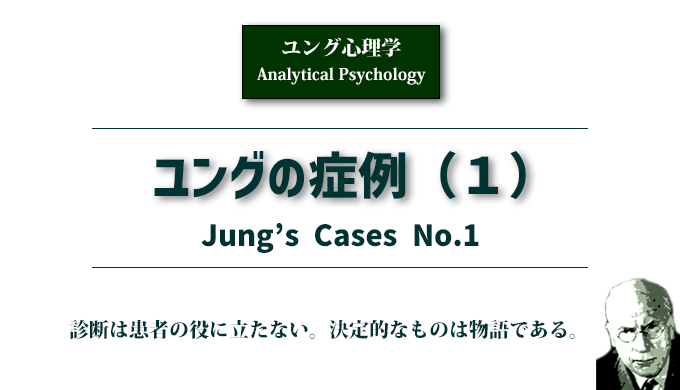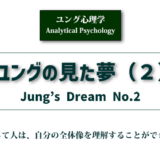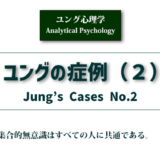ユングの症例を知ることで、ユングがどのように彼独自の心理学を確立していったのかが理解できる。ここでは『ユング自伝1』(みすず書房)で紹介されている事例を「前編」としてまとめた。
ユングが「催眠療法をやめるきっかけとなった事例」や「患者の不可解な言葉と行動に意味を発見した事例」は、ユングのターニングポイントといえる。各章の終わりには、ユングの心に残る言葉を記す。『ユング自伝1』(みすず書房)を参考文献として話を進めていく。
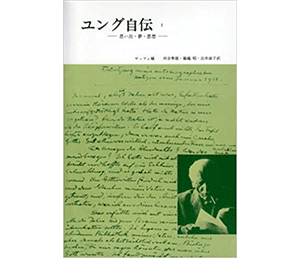
クリックするとAmazonへ!
症例:抑うつ症の婦人
ユングが精神科医になりたての頃の話です。病院に「メランコリー」(鬱病)にかかって、入院している婦人がいました。診断は分裂病(現在は統合失調症)でした。
ユングがこの婦人の担当医師となりました。ユングは分裂病の問題ではないと考えました。そこで婦人に「言語連想実験」を行いました。ユングの「言語連想実験」とは、ある短い言葉(「頭」「緑」「水」「歌う」「死」など)から自由に連想をしてもらい、その反応のしかたや反応速度からコンプレックスを見い出そうとする実験です。
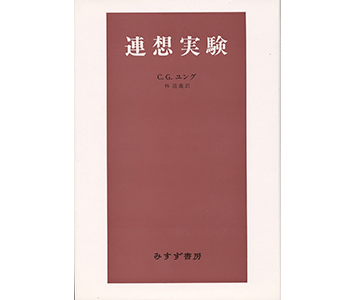
クリックするとAmazonへ!
自由に連想しようと思っても、人によって、言葉が出てこなかったり、おかしな連想をしてしまうことがあるのです。簡単に答えられそうなのに、言葉が出てこないとなると、それには「コンプレックス」が作用していると、ユングは考えました。
ユングは言語連想実験を通して、婦人の悲しく恐ろしい過去を知ることになります。
婦人は、ある男性に恋をしていましたが、彼が無関心なので自分からあきらめ、他の男性と結婚しました。ところが、5年後に昔友達と話すると、「片思い」は勘違だったと知ります。「君が結婚したとき、誰かさんはとてもショックだったんだよ」(p170)というのです。
この事実を知ってから婦人の抑うつ症は始まりました。

婦人には息子と娘がいました。入浴の時、娘が不潔な水をひたしたスポンジを吸っていました。彼女はそれを知りつつ、そのままにしました。すると娘は、腸チフスにかかって死んでしまったのです。
ユングは、言語連想実験をして、婦人が殺人犯であることを知ったのです。
彼女にこの結果を話すか話さないか。もし話すとしたら、症状がさらに悪化するのではないか。ユングは苦悩します。意を決して話すと、2週間後に婦人は退院し、2度と入院することはなかったのです。
連想検査が道を開くこともある。同様に夢の解釈やその個人との長く忍耐強い人間的な接触が道を開くこともありうる。治療においては問題はつねに全人的なものにかかわっており、決して症状だけが問題になるのではない。私たちは全人格に返答を要求するような問いを発しなければならないのである。
※上記の内容は『ユング自伝1』(みすず書房)p170−173に記載
症例:母親コンプレックスの男性
1904年から1905年にかけて、ユングはチューリヒ大学病院に実験精神病理学の実験室を設立します。
この実験室で、「言語連想」について学生とともに研究をします。この「言語連想」に関する研究がきっかけとなり、ユングは1909年に米国クラーク大学から招かれます。この時、フロイトも招かれていて行動を共にしています。

ユングの名は米国でも知られるようになり、スイスのユングのもとにアメリカからも患者が訪れるようになりました。以下の例は、そのアメリカから来たひとり男性です。
アメリカにいるユングの同僚の紹介でした。診断書には「アルコール中毒性神経衰弱」をと書かれてありました。ユングは、彼と話しあい「普通の神経症」だと判断しました。
連想実験をすると「母親コンプレックス」の持ち主であることがわかりました。
彼の母は大会社の持ち主です。彼は、母親の会社で働き、指導的な地位にいました。母親の支配下から逃れらない人生を送っているのです。母親は聡明な人でしたが「権力の化身そのもの」(p178)だったのです。
彼は母親が仕事に干渉してくると、重苦しくなる気持ちを発散させるために、お酒を飲みつづけていたのです。
簡単な処置をすると、彼は飲酒をやめることができ、治ったと考えました。ユングは彼がアメリカに帰る時に、「元の地位に戻ったらぶりかえすこと」を忠告していました。残念ながらユングの忠告の通りになりました。彼はアメリカに戻ると、またお酒を飲み始めたのです。
彼は母親には似ておらず、デリケートな性格でした。ユングは苦悩した末に、母親がスイスにいる時に、彼には内緒で「会社を辞めさせる」ことを母親に進言しました。ユングの進言は受け入れられました。
彼は激怒しましたが、その後、輝かしいキャリアを築き、成功をおさめることになります。アルコールからも解放されたのです。
数年間、そうした行為(会社を辞めさせること)だけが彼を自由にできるのだと確信してはいたものの、彼に内緒で診断書を書いたことで、この患者について罪の意識をもちつづけていた。そして、じっさい、いったん彼の解放が達成されると神経症は消失したのである。
『ユング自伝1』(C.Gユング みすず書房)p179
※(会社を辞めさせること)は筆者追記
※上記の内容は『ユング自伝1』(みすず書房)p177−179に記載
症例:松葉杖の中年女性(58歳)
この症例は、ユングが催眠療法をやめると決意することになった事例です。
ユングは、1905年、チューリッヒ大学精神科の講師に就任します。精神科医として仕事をしつつ、学生に対して講義を行うようになりました。
ある日、ユングは学生の前で催眠のデモンストレーションを行うことになりました。

催眠をかける相手は、松葉杖をつく左足に苦しい麻痺のある58歳の女性です。ユングが彼女に物語を求めると、女性は悲劇を語りました。ユングは途中で話をさえぎって催眠をかけることを告げると、彼女は、ユングが何も言わないのに、深いトランス状態に入ったのです。
彼女は催眠中に「無意識のかなり深い体験を表している夢」(p174)を語りました。30分して、ユングが催眠をとこうとしましたが、覚醒しようとしません。ユングは学生の前であわてることになります。
ところが目を覚ました彼女は、「私は治ったんです」といって、上機嫌で帰っていったのです。
次の年に、彼女はまた現れました。ユングに背中の激しい痛みを訴えました。彼女はまた自発的にトランス状態に入ります。すると、以前と同じように、痛みが消えたのです。
背中の痛みが現れたのは、ある新聞の予告を読んだ日からでした。その予告は、ユングの講義があることを知らせるものでした。
講義が終わった後、彼女と話してみると、彼女には精神科に入院中の精神薄弱の息子がいることがわかりました。その子は彼女のひとり息子です。そこでユングは考えました。
彼女の痛みが消失したのは、催眠の効果ではなく、「ヒーローの母親になりたい」という野心が働いていたからだと…。
精神薄弱になった息子のかわりにユングをヒーローにすることで、彼女は精神的な満足を得ようとしていたと分析できるのです。実際、最初の講義で彼女の症状が消えたため、「ユングは名医である」とその名声が高まっていました。
ユングは彼女に、自分のことを「息子のかわりにしている」という解釈を告げます。彼女はユングの解釈を受け入れました。その後、症状が再発することはありませんでした。
ユングは「真に治療的な体験だった。─言うならば話足の最初の分析だったのである」(p176)と書いています。
この事例があって、ユングは催眠を使わないようになるのです。
私は患者の自然な性癖がどこへ彼を導いていくのかそれを患者自身から学ぶことにより多くの関心を抱いていたのである。それを見つけ出すためには、夢やその他の無意識の現れを注意深く分析してみることが必要であった。
※上記の内容は『ユング自伝1』(みすず書房)p174−177に記載
症例:友人を殺害した婦人(医者)
この事例の患者は、医者をしていたという婦人です。みるからに上流階級に属している人でした。
彼女は身体的に辛い症状があるのではなく、「ただ相談したい」というのでした。話を聞くと、彼女の驚くべき過去が明らかになります。
ユングのもとを訪れた日から、ほぼ20年ほど前、彼女は友達の夫と結婚するために、その友達を毒殺したと告白したのです。もちろん毒殺のことは、誰にも話したことはありません。
目的の男性と結婚できましたが、若くして夫は亡くなってしまいます。
夫との間には娘がいました。娘は成人すると母親のもとを離れようとします。結婚した後、音信不通となります。彼女は乗馬に熱心でした。ところが乗馬をすると馬がいらだつため、乗馬をあきらめなければなりませんでした。さらに、かわいがっていた犬(ドイツ系のシェパード)は、麻痺にかかってしまいます。

次から次にと不可解で不吉なことが起こり、ユングに「ただ相談したい」と訪れたわけですが、彼女は自分の毒殺という罪を誰かに告白したかったわけです。
ユングは「彼女は殺人犯であるが、それに加えて彼女自身をも台なしにしてきたのであった。そうした罪を犯した者は、彼自らのまたしいをも破壊するものである」(p181)と書いています。
罪を犯した時、黙っていても、わからないだろうと考えていても、相手に伝わってしまうものがあるのです。
なぜなら、私たち人間は、言葉を通してだけでなく、心と心で、無意識レベルの会話をしている存在だからです。
結局それは現れてくるものなのである。ときにはまるで動物や植物さえもそれを「知っている」かのようにみえることもあるのである。
※上記の内容は『ユング自伝1』(みすず書房)p181−182に記載
症例:手と腕をリズミカルに動かす老婦人(75歳ぐらい)
この事例の患者は、ユングの病院に50年ほど前に入院しました。75歳ぐらいの老婦人です。50年前のことですので、ユングも入院時のことを知りません。
老婦人は話すことができず、コップ1杯のミルクを飲むのに2時間かかります。食事以外の時には、手と腕をリズミカルに奇妙に動かしていました。講義で彼女は、早発性痴呆(現在の統合失調症)のカタトニー型と紹介されていました。
なぜ彼女は、手と腕をリズミカルに動かし続けるのか。
当時の精神科医たちは、彼女の意味不明な動作を「病気だからそういうものだ」と決めつけ、それ以上深く考えようとしませんでした。ユングは違いました。「私は精神医学の主な仕事、病める心の中で起こっている事柄を理解することと考えていた」(p183)のです。
ユングは、年老いた婦長を訪れ「いつもああしているのか」と質問しました。婦長は、「私の前任者が、彼女はいつも靴を作っているんだと言っていました」と答えました。ユングは、彼女の事例史をもう一度調べます。そこには彼女が「靴直しの動作」をすることが書かれてありました。
この患者が亡くなった時、葬式に来た患者の兄に、妹がどうして病気になったのかを質問してみました。すると、彼女が、ある靴屋に恋をしていて、彼が彼女を捨てた時に発病したことがわかったのです。
つまり、「病気だからそういうものだ」ではなかったのです。彼女の動作は決して意味不明ではなく、原因があったのです。彼女の動作には意味があり、それは恋人との「同一視」だったのです。

「同一視」とは、精神分析の用語で、心を守ろうとする防衛機制のひとつです。受け入れがたい感情や状況がある時に、自分を他者と重ねて、自分のことのように感じることで自己評価を高めるのが「同一視」です。
例えば、憧れのアーティストのダンスを同じように踊って、SNSにアップすることで満たされるのは「同一視」のひとつと考えられます。
ユングはこの事例をきっかけに、不可解な患者の言葉や行動にも意味を見出そうと奮闘することになります。
臨床的診断はそれが医者に一定の方向を与えるので重要である。しかし、診断は患者の役に立たない。決定的なものは物語である。というのはそれだけが人間の背景の苦しみを示し、その点でだけ医者の治療が作用しはじめることができるからである。
※上記の内容は『ユング自伝1』(みすず書房)p182−183に記載
(文:松山 淳)
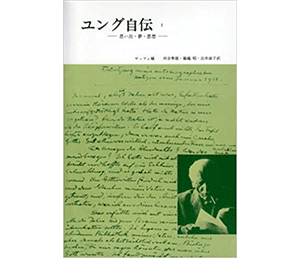
クリックするとAmazonへ!